①「昔の夏祭りの屋台を模したそれらを見て、実物を見たことがないはずの子供たちが、なつかしいね、と盛んに言っていた。」(2)「真夜中をすぎたころ、流星がいくつか空を横切り、そして、宇宙へ飛び立った航空機の光も見えた。明るすぎる星みたいなその黄色い光は、音もなく、正確に軌道を滑って、彼方へ消えた。」(3)「敷地を囲んでいた外国産の木々だけは伸び続け、高層ビルほどの高さになった。」
②「百年と一日」を読んで、人と場所の関係というのを小説の中でこれほど意識的に読んだことはなかった。場所や空間というのは不安定なものだし、不気味なものでもあると思っている。それは人の存在の面影や、時に顔だったり、営みの痕跡だったり、あるいは場所に引かれた導線が浮かんできたり、モノの配置から受け取る、過去の誰かの眼差しの交点に自分が立っているからかもしれないという感覚。そういった印象が漂っていると感じるからでもあると思う。しかし同時に、空間なるもの自体が私たちの幻想なのかもしれない。かつて人が集まり、モノが運ばれ、行き交い、また通り過ぎっていった時間や記憶が交差するような場所。それらの時間と空間を移動していく感覚で「百年と一日」を読んだ。
確かにこれはどこかの誰かのあったかもしれない物語だと思った。誰かの記憶が、いつのまにか私の経験になっているかもしれない。不気味だけど、そんなこともあるかもしれない。
(1)「昔の夏祭りの屋台を模したそれらを見て、実物を見たことがないはずの子供たちが、なつかしいね、と盛んに言っていた。」この「なつかしさ」は偽物だろうか。そう思わされているのだろうか。再現されたものだからだろうか。模したもの、と、実物、との間にはどんな差があったのだろうか。読みながら不思議に思った。ハリボテの書き割りのようなものだろうか。それが「なつかしいもの」だということを子供たちは知識で知っていただけなのだろうか。歴史はなつかしさだろうか。「新しきなつかしきもの」があるとしたらどんなものだろうかと思った。
(2)「真夜中をすぎたころ、流星がいくつか空を横切り、そして、宇宙へ飛び立った航空機の光も見えた。明るすぎる星みたいなその黄色い光は、音もなく、正確に軌道を滑って、彼方へ消えた。」海と空は似ていると感じた。夜の海に見える船の明滅する光。水平の視線から一気に垂直に見上げる視線へ。海から空、宇宙への移動のスケールにぐっと来た。暗闇の中に光を追う。そして最後には水中の中に何かを見る。
(3)「敷地を囲んでいた外国産の木々だけは伸び続け、高層ビルほどの高さになった。」
これはあるいは不気味な話だ。敷地を囲む形に生えた植物の空間。建物はなくなっても、成長しつづける木々の時間。なぜこんなところに場違いな木が生えているんだろうと考えたときに、ふっと見えてくる空間の形。この形は、木々が垂直に伸びていくほど、実際の建物の高さを越えて、浮かび上がる。確かにこの風景の経験があるかもしれない。アスファルトの地面だけが残る広大な平面。駐車場の白いラインがかすかに見える。外国産の木々が囲む。夕日が沈みかけている。
80年代から全国的なリゾートやテーマパーク建設が加速し、バブル崩壊をむかえたその後などの一連の狂躁的な時代の残滓として、よく見られる風景なのかもしれない。しかし、そこにしっかりとした手触りを感じた。確かにリゾートやテーマパークによって一喜一憂する地元地域の困惑も思い浮かぶ。だけど確かにあの時、あの場所に人もモノも通い、楽しかったし、美しかったのかもしれないと思う。これまでも、これからもこのような場所は生まれては消えてを繰り返していくかもしれない。でも僕はそんな話が、そんな風景がきっと好きなのだろうと思う。
ソートン・ワイルダーの「わが町」という戯曲を思い出す。なんてことない町とそこに暮す人々の物語。町とは一つのキャラクターなのかもしれないと思うことがある。僕は演劇をやっている。そんな町の時間が好きだ。
僕は福島県と東京を行き来している。浜の町の図書館に行って、町の広報誌を過去数十年分パラパラと見ていたことがあった。この町で1986年の正月に不慮の事故でなくなった詩人であり彫刻家がいたことを知って、その人の記事はないかと調べていた時だった。町の運動会や文化祭、誰かが結婚した話、亡くなった話、表彰された話、昔話なんかが、まさしく小さな町の平凡な日々の記録としてあった。
残念ながらその詩人であり彫刻家の記事はどこにもなかったけれど、年代ごとにファイリングされた数十年分の分厚い広報誌の束が、相変わらず平凡に、2011年2月号まで続いていた。3月号はなかったし、かわりに新聞記事がたくさん挟み込まれ、町も地域もバラバラに引き裂かれたことを物語っていた。あの震災がなければ、この町のことなど一生知らなかっただろうし、気にもとめることもなかっただろうと、過去の広報誌の平凡な日々の途方もなさから、僕はその時そう思った。原子力緊急事態宣言は10年間継続中だ。
本当に小さく、これといった観光資源がある訳ではなかった港のある町のこと。僕はこの町でフィールドワークを続けながら、町の歴史や人々の生活史を見ては聞いたりした。不思議な話もたくさんあった。何気ない場所の思い出話もあった。巨大な防潮堤が海と陸を隔て、ある人は、海が見えなくなった、と嘆き、ある人は、もう海なんて見たくないからよかった、と言った。そして町民の多くが帰還することはないだろう。またある人は、この町はこれからよそもんだらけになる、と言って、彷徨っていた動物たちを引き取って、世話をしながら山林に一人で暮らしていたりする。
この町は、かつて見通せなかった山々に夕日が沈むのがきれいだ。海も山も空も広くて互いに隣り合っていて壮観だ。明かりの少ないこの町で、夜空に小惑星探査機が帰還するのが見える。月のない夜には、明かりがみんな海に吸い込まれる。
人も時間も場所も通り過ぎていく。うつろいながら今でも寂しいその町の港を思い出して、次の、また次の世代で、防潮堤で遊ぶよそもんの子供たちのことを考えた。
③アトリエには「パーシパエの牛」が完成させてあった。先生は一息ついたところで、海岸に降りて砂浜を歩いた。アトリエは20mある崖の上にあった。砂浜にはその崖に沿ってテトラポットの群れが連なっている。そこから僅かに離れて、波間からまっすぐ海食柱がそびえている。海食柱は地元で「ろうそく岩」と呼ばれていた。頭に松の木が生い茂っていた。小浜海岸は景勝地の、美しい海水浴場として地元民に愛されている場所でもあった。
先生は、昨晩、新年会を兼ねて地元の教室の生徒たち数人と飲み明かしていたが、朝には熱した鉄を張り合わせて、作品の最後の行程に取りかかっていたのだった。部屋は、鉄を熱しては冷やすを繰り返して蒸し風呂状態になっているので、外に出て海から吹く風に当たった。冬の風が体に溜まった熱をあっという間に冷ましていく。そうやってよく海岸を散歩するのが好きだった。
その日、1986年1月3日午後2時頃だった。先生はテトラポットの上を歩こうとした。なぜそうしたのかはわからない。何かを見ようとしたのだろうか。テトラポットの上から足を滑らせて、体を強く打ちつけ、隙間に転落してしまったのだった。顎は砕けて血が口から溢れ出した。なんとかそこから這い出ることはできたが、立つことが出来なかった。これ以上動くことも出来なかった。助けも呼べない。人目から外れたテトラポットの陰で、凍てつく寒さの中、先生は死んだのだった。あまりに唐突な死だった。享年69歳。
先生は井手則雄といった。詩人であり彫刻家だった。鉄を使った抽象的な彫刻作品から「鉄の詩人」と呼ばれていた。朝鮮京城府で生まれたが、幼少期に父親の故郷である長崎に移り住んだ。その後上京して東京開成中高を卒業し、東京美術学校の彫刻科に入学した。大学卒業後しばらくして戦争にも従軍した。海軍兵だった。戦場でいくつかの詩を書いて、戦後それを詩集「葦を焚く夜」として出版した。詩人としては戦後詩の同人誌「列島」(現「詩と思想」)を創刊し、彫刻家としては「前衛美術会」の結成メンバーにもなった。1952年の皇居外苑「血のメーデー事件」で、デモ隊として参加して警察予備隊と激しく衝突した人でもあった。
そんな経験の持ち主であっても、まったく穏やかな印象だった。理論家であった先生の語り口は冷静で、かと思えば二カッと歯を見せて無邪気に笑った。立ち姿もふるまいもスマートに見えた。
先生がこの町に最初に来たのは、念願の美術教育の研究に本腰を入れる環境が整って、1972年の12月に宮城教育大で美術科教授に就任して間もない頃だった。
町の文化センターで講演会を行った。その日の内に、この町がすっかり気に入ったのだった。海と山は近く、坂や台地の多い地形と、過ごしやすい気候が肌にあった。海岸の崖の上に立って、海上の気流を体に感じて、そこからの眺めもさらに気に入った。ギリシャ文化に造詣のあった先生は「まるで日本のエーゲ海ですね」とおどけながら地元の人々と話した。「水平線が此処からは彎曲して見えるほどだ。果てまでも青い海よ」
地元で世話をしてくれた花房に「私が死んだら、海を眺めるこの崖の上に墓を立てたいな。その前にこのあたりにアトリエを作りたい。さっそく誰か都合よく土地を用立ててくれる人はいませんかね」と頼んだ。話はとんとんと進み、観陽亭という温泉旅館の裏に土地を借りて「井手則雄セミナー館」を建てた。住まいは東京だったが、宮城までの中間地点のこの町はちょうどよかった。その頃東京の南荻窪で自身が運営する「造園美術コンサルタント」が手詰まりになって、そろそろフェードアウトし始めた頃でもあった。
このアトリエで地元の人々を相手に美術教室を開き、時に宮城教育大の学生たちを呼んで合宿もした。宴会もたくさんやった。東京から知り合いの作家や美術家も訪ねてきた。潮風の吹くこのアトリエで、酸化や風化に耐える鉄の使用法の研究もしていた。
鉄の、その暴力性と、熱によって変形する柔軟性に惚れ込んだ。
「鉄を溶かしていると、この基幹産業の生産材が、人殺し道具への残忍な意思を、中世そのままに受けついでいることを感じます。物質が意識をつくりかえると信用しているぼくは、こやつもデリカな抒情と敗北の意思を持つことを、思いしらせてやりたいと思いました。」
先生は時間を忘れて砂浜に横たわって、ずっと波を眺めていることがあった。その日は子安橋の上から海を眺めながら、美術教室の生徒である猪狩と話していた。猪狩は地元出身で、大学は東京の農業系の大学に入った。卒業後3年ほどサラリーマンをしていたが、地元に戻って農協に勤めていた。耕耘機やトラクターを修理する仕事や板金屋の手伝いもしていた。実家は海にほど近い農家だった。
先生は「波を横から見ているとね。トンネルになる瞬間があるんだよ。波は空洞を抱え込んでいるんだね。ずっと見ていても飽きないよ。」先生はこの波の空洞性を鉄で扱えないかと考えていた。空洞をそのうちにたたえた鉄のムーブマンと沈黙の空間。
「ここの海岸は日本では唯一かもしれない。様々な角度から大小たくさんの波が織り重なっている。」
「ここは遠浅ですからね」猪狩は答えた。彼は子供の頃によく海岸に海水浴に来ていた。祖父が付き添って来てくれた時に、「おらがこどもん頃は崖なんかじゃなかったんだぁ。砂浜はもっとずっと沖合にあってよぉ。集落だってあったんだよ。それがあっという間に後退しちまって、集落のあった場所は海ん中沈んで、ここいらも急に崖になっちまった。」と語っていたことを今でも覚えていた。
「もうすぐ河口の向こうに新しい漁港が出来ますよ」
「そうらしいね。するとあっちの漁港はどうなるんだい?」
「あそこはもう危ないですからね。崩れかかってて。いずれ廃港になるでしょうね」
「そういかい。」
明治時代にたった1人で漁港を作った男がいた。私財をなげ売って、男はツルハシをふるって1人で岩壁を掘りぬいた。天然入り江の日本一小さな漁港が出来た。しかしそこはもう使えなくなくなるだろう。新しい漁港は原発建設に伴う保障金で作られる。
日が沈みかけていた。「ドライブに行こうよ。運転してくれないか」アトリエの助手でもあった猪狩は、車に先生を乗せることが何度かあった。助手席に座った先生は車を走らせてしばらくして、いつものように五木の子守唄を口ずさみはじめた。
小浜台という丘陵台地の北側まで車を走らせて、杉の森を西に抜けて国道を横切り、阿武隈山系がよく見える線路沿いの場所に着いたあたりで車を引き返した。ぐっと勾配を下ってアトリエ近くに差し掛かったあたりで、操業間近の第二原発の排気筒が、町の南側の台地にそびえているのが見える。原発は中世の城廓跡の上に建っていた。排気筒は町のランドマークになりつつあった。
「原発は反対だよ」先生は言った。猪狩は少し驚いて、はい、とだけ答えて何も言うことが出来なかった。初めてその口から聞いた言葉だった。先生は日本で初めて原子炉が稼働した時、「第二の火」という詩を書いて発表していた。
先生の死後まもなく、回顧展が東京で開催された時、猪狩は「ポセイドン・アイゲウス」と題された作品を見た。波間に立つ何本かの柱をイメージした時、あの原発の集中式排気筒かもしれないと思った。排気筒はアトリエからもよく見えた。
1986年の8月に、崖の上のアトリエの敷地内に、地元の有志によって黒大理石の詩碑がたてられた。海が一番よく見える崖の縁に。この町の風景をうたった先生の詩が刻まれた。この場所に墓はたてられることはなかった。井手則雄セミナー館の建物はその後跡形もなく解体され、更地になった。
先生が死んでから25年後、大震災が起きた。地震と津波が襲い、北の隣町では第一原発がメルトダウンを起こした。地域住民は避難を余儀なくされた。この町にある第二原発は寸前のところで危機を脱し、崩壊は免れた。
この町では最大21mの大津波が襲った。漁港はことごとく破壊され、民家や商店は瓦礫となった。アトリエの隣にあった観陽亭も被害を受けた。崖も大きく削られた場所があった。アトリエの目と鼻の先にあった「ろうそく岩」も、根元から折れて僅かに土台を残すのみとなった。
町のシンボルでもあった「ろうそく岩」が、折れたことを知った地元の人々は残念がった。古い漁師たちは、自分たちの若い頃には「ろうそく岩」はまだなかったことを話していた。この40年くらいで、崖が削れて、次第にろうそくみたく細くなっていったのだと口を揃えた。漁師のうちの1人の仮説では、北の隣町に第一原発が出来て、海に突き出した湾港が海水の流れを変えて、こっちの崖を削り始めたのだと言った。長年海を見てきたその漁師の仮説に「あの人がそう言うんだったらそうかもしんねぇ」と話を聞いた人々は思った。そこに居合わせたある若者は「原発に火がともって、ろうそくも立って、原発が吹っ飛んで、ろうそくも消えたってことか」と冗談めかして言った。
先生のアトリエのあった場所も、いつも散歩し、波をみつめた場所も、全く様変わりした。あの詩碑も行方不明になった。先生が亡くなったテトラポットの群れにひっかかるように、自力航行能力のない石船が漂着していた。津波で60キロ南の港から流されてきたのだった。船を所有する運航会社は回収を拒否した。船は赤く錆び付いた鉄の塊となった。町民が避難し、数年間誰1人いなかったこの町で、船は取り残され段々と自重で砂の中に沈みつつあった。
それから6年がたって、町は一部を除いて避難指示が解除された。除染のため田畑の表土は削り取られ、家々は解体された。空き地が増え、疎らに残った建物もあったが、見通しのよい景観になっていった。フレコンバックにまとめられた瓦礫や廃棄物は、焼却処理された。それら粉末にされ塵となったモノたちは、コンクリートに固められ、山中に貯蔵されていった。
先生には息子がいた。息子は宇宙科学の道に進み、やがてNASAの研究員を経て、JAXAの小惑星探査のプロジェクトに参加することになった。専門が「宇宙塵うちゅうじん」だった彼は、探査機に搭載するサンプラーとそのシステムを開発し、持ち帰られたサンプルの分析を行うことになっていた。彼が関わった探査機は小惑星に向けて出発し、到着後小惑星の地表からサンプルを採取することに成功した。帰路につき、7年ぶりに地球に帰還した探査機はサンプルの入ったカプセルを分離した。大気圏に突入し空を滑っていくカプセルの光の筋が、明かりの少なくなったこの町の、南の夜空を抜けていくのが海岸からはよく見えた。先生が亡くなって35年目、震災から10年目になろうとしていた。
町には、先生の残した野外彫刻が一つだけある。「萌える」と題されたその彫刻は、数年間帰還困難区域内にあった。今は区域の境界になっているバリケードを背中にして、ロータリーの中央に、町の開花基準木の桜と共に並んで立っている。その作者が井手則雄であることを知っている町の人は誰もいない。そして先生を知る人は、町にはもういない。
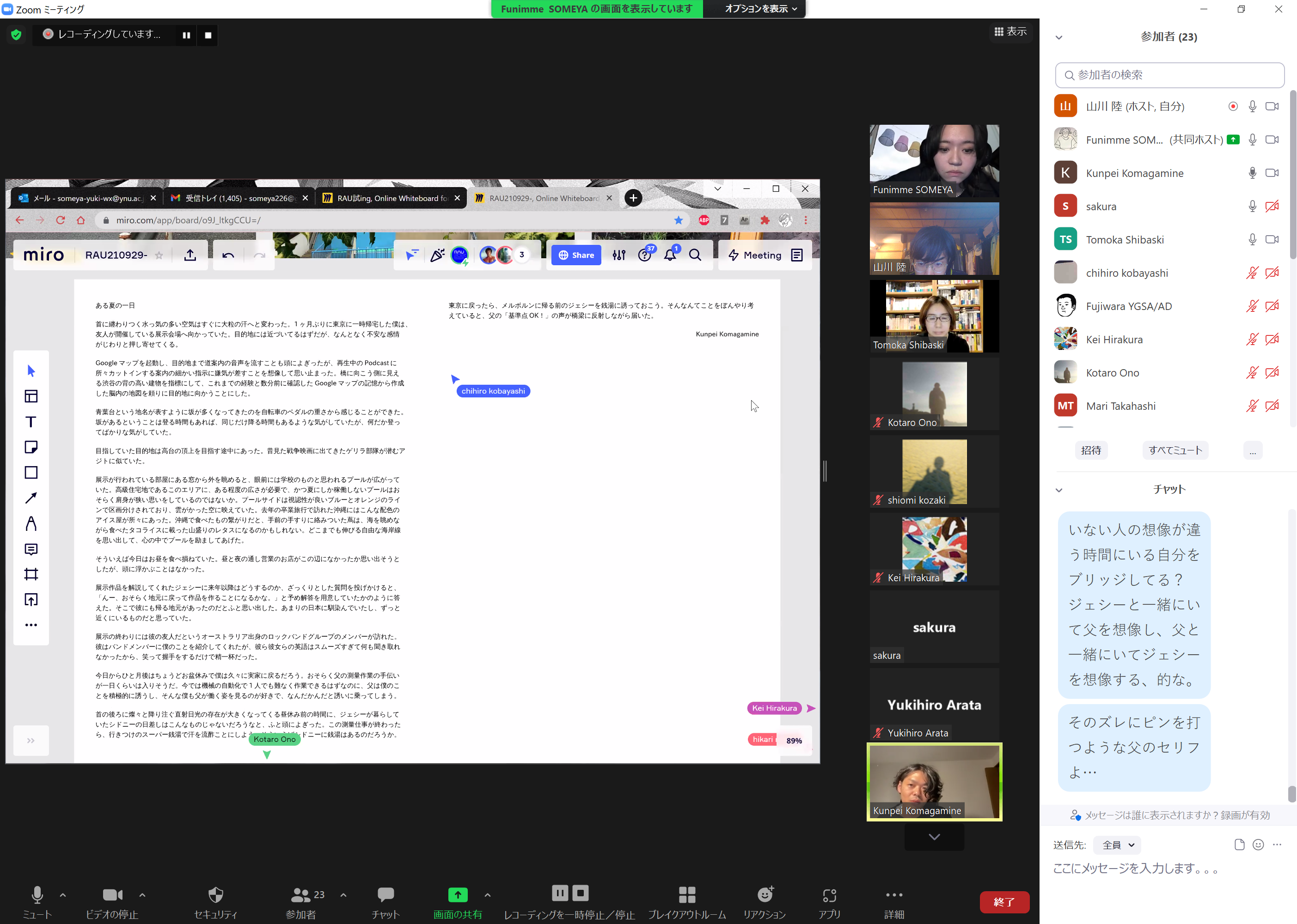
WS2 土地と身振り
「土地と身振り」は、小説家・柴崎友香氏の短編集『百年と一日』に応答することからワークショップを開始しました。ある場所にある百年と一日のような時間の巡りが描かれた本作を元に、各メンバーの個人的な思い出を語ることから始まり、自身の写真と他者の写真の組み合わせからフィクションを書いたり、徐々に自分自身から離れたところへテキストを書きおく試みが続きました。
主観的に時間・空間を自由に並べたり動きまわれるテキストを通じて、主観的な頭の中にある経験と土地を結ぶものとして、具体的な身振りのあることが分かってきました。「土地と身振り」とは、「主観ー身振りー土地」と結ばれたものであり、映像の制作において主題となってきた「私はどこにいるのか」を表す方法と言えそうです。
キヨスヨネスク『百年と一日』P68-「埠頭からいくつも行き交っていた大型フェリーはすべて廃止になり、ターミナルは放置されて長い時間が経ったが、一人の裕福な投資家がリゾートホテルを建て、たくさんの人たちが宇宙へ行く新型航空機を眺めた」への応答
上田和輝『佐々木が走った道』
同じ高校に通う佐々木と上田は、同じ大学の同じ学科を受験するために同じ飛行機で東京に来て、同じホテルの隣同士の部屋に泊まることになった。二人は二年生の時に同じクラスだったから話すこともあったし、受験の間、一緒に行動することになった。二人とも、東京に来るのは初めてだった。
全ての試験が終わって、二人は疲れた頭で空港に向かっていた。「快速と急行ってどっちが早かと?」「さあ。1時間もあっし間に合うど。」人生で数えるほどしか使ったことが無い鉄道交通のしきたりについてぼんやりと不安を浮かべながら、行きの電車では参考書に落としていた視線を車窓に向けて、見たこともない巨大な街並みが流れていくのを眺めていた。 電車が空港の駅に着いたのは、出発予定時刻のちょうど30分前だった。出発ロビーへのエスカレーターを駆け上がったが、チェックインは締め切られていた。
振り替えの便を探すから、ここで待っているように、と空港職員に言われたきり、数時間経った。すべての便の受付が締め切られ、売店も閉まったあとのがらんとした空間に、数人が取り残された。
佐々木は、どうせ帰るのが明日なら、各々東京観光にでも行けばいいと考え始めていた。それとなく上田に提案しても、生真面目な上田はひたすら職員を待つべきだと答える。口数の少ない二人は、二言、三言交わすばかりで会話が深まらず、事態は膠着していた。 一緒に取り残された大人たちが寝支度を始めたころ、ようやく空港職員がやって来た。空港職員は、未成年をロビーに泊めるわけにはいかないから、宿を手配した。明日、7時台の振替便に遅れないように戻って来るように、と言いながら手書きの地図を手渡した。地図には、空港の隣町の駅から、宿までの道が描かれていた。
空港の隣町の駅は、小さな駅だった。改札の外の広場は駐輪場に占められて、車一台入る隙間もない。駅を取り囲む住宅を見回した佐々木は、東京のくせに自分が住んでいるマンションよりも低い建物しかない、と思った。
地図に沿って住宅街の路地を曲がると、宿の行燈が見えた。隣の住宅と変わらないしつらえの玄関に、番頭のおばさんが待ち構えていた。事情を聞いていたのか、番頭は学生服姿の二人に驚く様子もなく、部屋まで案内すると、「飛行機に間に合うように起こしに来るから、ゆっくり休みなさい。」と言った。それでも再び乗り過ごす不安に囚われていた上田は、風呂も食事も取らず早々と床についた。
一方の佐々木の頭の中では、不安とは違う空洞な何かが渦巻いておさまらなかった。今日で、高校生活が事実上終わった。滑り止めの大学には受かっていたから、もう勉強に追われることはないし、登校日も残り何日もない。ひと月後には、どこかの街で大学生になっている。何一つ実感がないまま、今は知らない街で、古びた民宿の六畳一間に閉じ込められている。
佐々木は、番頭の目を盗んで宿の外へ出た。道が途切れたり、曲がったりして見通しが悪い住宅街を、漫然と歩いた。東京の夜道は明るかった。狭い路地にも街灯があることに、佐々木は驚いた。
歩いていくと、堤防にぶつかった。堤防の上に登ると、今まで気配を感じなかったことが不思議なほどに大きな川があった。川をまたぐ高速道路の騒音に混じって、川面から、ゴトゴトと何かがぶつかる音が聞こえる。堤防の下を見下ろすと、暗闇に大きな影が揺れていた。「釣り船だ。」佐々木は思わず独り言ちて、自分が釣りが好きだったことを思い出した。
佐々木が経験のないバドミントン部に入ったのは、釣りと手首の動きが似ていると思ったからだった。バドミントン部は、勉学優先でスポーツにやる気はない、たむろしたいだけの男子の集まりだった。にも関わらず、高校の応援団の団長をバドミントン部の部長が務めるという伝統があって、三年生のはじめにジャンケンで負けた佐々木は、その年の団長として、集会での校歌斉唱のたびに全校生徒の前で指揮をさせられた。そんな理不尽な因習とも、もう関係がない。
堤防の上を河口に向かって歩いていくと、橋に行き当たった。橋の向こうは、空港の土地だった。橋を渡ると、目の前に大きな鳥居が建っていた。狛犬も賽銭箱もなく、鳥居だけがあった。平坦な土地の彼方に、空港のビルの灯りが見える。鳥居は空港の方でもなく、何もない、海の方を向いている。
奇妙な光景の前に立ち尽くしていた佐々木の横を、自転車が通り過ぎた。空港の方へ、背中に釣り竿のケースを抱えて走っていく。この先に釣り場があるんだ、と思った佐々木は、鳥居を通り抜け、その背中を追った。 自転車を追った先には川沿いの遊歩道があった。空港の土地に沿って、長々と続いていた。佐々木は遊歩道のベンチに座り、そこに釣り人が増えていくのを、ただ眺めていた。空が白んでいくとともに、遊歩道は賑わい、対岸の工業地帯は輝きを失っていった。 うたた寝をしていたのか、気がつけば時計は6時を指そうとしていた。急いで宿に戻らないといけない。佐々木は朝陽を背中に感じながら、朱色に染まる鳥居に向かって走った。始発の飛行機が、それを追い越して行った。
四年後、上田は大学の物好きな友達の企画で、夜通し歩き倒して朝日を拝む会の一行に参加していた。川沿いに歩き、河口の空港の屋上から朝日を見る行程だったが、あの日上田と佐々木が泊まった民宿を探すために、空港の隣町に寄り道をした。 駅からの記憶を辿っても、宿は見つからなかった。心当たりのある付近の住宅街をぞろぞろ歩いていると、誰かが神社を見つけた。あの日、朝起きると、佐々木はすでに出かける支度をしていた。「早かな。」と声をかけると、佐々木は「神社まで走ってきた。」と答えた。確かに神社はあった。しかし、記憶が間違っていなければ、わざわざ走って行くような距離でもない。
あの日以来、上田は佐々木と話してもいないし、連絡先も知らなかった。上田が知っている佐々木の消息は、一緒に受けた大学には落ちて、滑り止めの大学に行ったこと。そして、釣りばかりして大学をサボっているという噂だけだった。
諦めて空港に向かって歩き始めた一行は、橋を渡り、大きな鳥居に直面した。奇妙な光景にはしゃぐ一行を横目に、上田は鳥居のふもとにあった解説を読んだ。
空港の土地は、200年ほど前の干拓により開墾された。当時この一帯は遠浅の海で、漁業が盛んだった。はじめ、塩害に悩まされた新田の豊作を願って建立された神社は、遠浅の海がレジャーとして人気になると、門前町を作って大いに賑わった。しかし戦争があって、この土地には大きな空港が建設されることになり、神社は立退を求められた。遠浅の海は埋め立てられ、対岸も工場のために埋め立てが進み、海の環境が変わって漁業も廃れた。今は神社の鳥居だけが居残って、名残を惜しんでいる。
説明を読んだ上田は、自分が生まれた土地のことを思い出していた。上田が生まれた土地でも、200年ほど前から干拓が盛んに行われた。干拓地には大きな川が流れ込み、水が豊富なため工場が作られるようになった。戦時中は軍需により工場は人を集め、街は賑わった。しかしそのせいで海は汚れ、昔ながらの漁業は衰退した。今でも、塩害に悩まされる農地を差し置いて、川岸の巨大な工場が、寂れた街の経済を支えている。
空港から運ばれる人々も、工場から運ばれていく製品も、この街に降り立つことはない。上田がそんなことを考え始めていると、「日の出まであと10分だって!」という誰かの掛け声とともに、一行は空港に向かって走り始めた。
若林さち『野球場の会話』
大阪ドームって。京セラドームでしょ。
確かに、そんな話聞いたことない。すごいね。
たまに、こうやってまっすぐ歩いているだけなのに、地球上で自分が一番すごい体験をしているぞって思うときがある。 いつからそう思うようになったかは分かんないけど。
なんばパークスって、大阪球場が解体された更地の上にできたやつだよね。懐かしい。大阪球場でプロ野球の試合があった頃って、まだ私たち生まれてないよね。懐かしい。
そういや、「戦前」とか「戦後」って言うときの「戦」って、私は第二次世界大戦の意味で使ってるんだけど、この前「どの戦争?」って聞かれちゃった。
そうだよね。キリストが生まれたのも多分最近。
駒ヶ嶺薫平『ある夏の一日』
ある夏の一日
首に纏わりつく水っ気の多い空気はすぐに大粒の汗へと変わった。1ヶ月ぶりに東京に一時帰宅した僕は、友人が開催している展示会場へ向かっていた。目的地には近づいてるはずだが、なんとなく不安な感情がじわりと押し寄せてくる。
Googleマップを起動し、目的地まで道案内の音声を流すことも頭によぎったが、再生中のPodcastに所々カットインする案内の細かい指示に嫌気が差すことを想像して思い止まった。橋に向こう側に見える渋谷の背の高い建物を指標にして、これまでの経験と数分前に確認したGoogleマップの記憶から作成した脳内の地図を頼りに目的地に向かうことにした。
青葉台という地名が表すように坂が多くなってきたのを自転車のペダルの重さから感じることができた。坂があるということは登る時間もあれば、同じだけ降る時間もあるような気がしていたが、何だか登ってばかりな気がしていた。
目指していた目的地は高台の頂上を目指す途中にあった。昔見た戦争映画に出てきたゲリラ部隊が潜むアジトに似ていた。
展示が行われている部屋にある窓から外を眺めると、眼前には学校のものと思われるプールが広がっていた。高級住宅地であるこのエリアに、ある程度の広さが必要で、かつ夏にしか稼働しないプールはおそらく肩身が狭い思いをしているのではないか。プールサイドは視認性が良いブルーとオレンジのラインで区画分けされており、雲がかった空に映えていた。去年の卒業旅行で訪れた沖縄にはこんな配色のアイス屋が所々にあった。沖縄で食べたもの繋がりだと、手前の手すりに絡みついた蔦は、海を眺めながら食べたタコライスに載った山盛りのレタスになるのかもしれない。どこまでも伸びる自由な海岸線を思い出して、心の中でプールを励ましてあげた。
そういえば今日はお昼を食べ損ねていた。昼と夜の通し営業のお店がこの辺になかったか思い出そうとしたが、頭に浮かぶことはなかった。
展示作品を解説してくれたジェシーに来年以降はどうするのか、ざっくりとした質問を投げかけると、「んー、おそらく地元に戻って作品を作ることになるかな。」と予め解答を用意していたかのように答えた。そこで彼にも帰る地元があったのだとふと思い出した。あまりの日本に馴染んでいたし、ずっと近くにいるものだと思っていた。
展示の終わりには彼の友人だというオーストラリア出身のロックバンドグループのメンバーが訪れた。彼はバンドメンバーに僕のことを紹介してくれたが、彼ら彼女らの英語はスムーズすぎて何も聞き取れなかったから、笑って握手をするだけで精一杯だった。
今日からひと月後はちょうどお盆休みで僕は久々に実家に戻るだろう。おそらく父の測量作業の手伝いが一日くらいは入りそうだ。今では機械の自動化で1人でも難なく作業できるはずなのに、父は僕のことを積極的に誘うし、そんな僕も父が働く姿を見るのが好きで、なんだかんだと誘いに乗ってしまう。
首の後ろに燦々と降り注ぐ直射日光の存在が大きくなってくる昼休み前の時間に、ジェシーが暮らしていたシドニーの日差しはこんなものじゃないだろうなと、ふと頭によぎった。この測量仕事が終わったら、行きつけのスーパー銭湯で汗を流酢ことにしよう。そういえばシドニーに銭湯はあるのだろうか。東京に戻ったら、メルボルンに帰る前のジェシーを銭湯に誘っておこう。そんなんてことをぼんやり考えていると、父の「基準点OK!」の声が橋梁に反射しながら届いた。
たかすかまさゆき『あっちとこっち』
「はじめて太平洋を見たときは、そりゃもう怖かった。<海>って言えば内海しか知りませんから、島影が見えんのはもう、恐ろしゅうて恐ろしゅうて。足が竦む思いでしたよ。
「海についての思い出ですか?そうですねぇ。もともと山育ちですからそんなにありませんが……そういえば、母方の大叔父が昔ボートを持っとりまして。浮き船にエンジンが付いたような小さいもんでしたけれど。子どもの頃一度だけ乗せてもらったことがありましたよ。大叔父が運転するボートに父と兄といっしょに乗り込んで、海釣りをしたんですけどね。昔っから乗り物に弱いもんですから、もう酔って酔って仕方がなくって。げぇげぇ吐きっ通しで釣りどころじゃなかったですよ。それでもちゃっかり何匹かは釣り上げましてね。海の魚っていうのは鱗がね、ずいぶん綺麗な色をしとりますよねぇ。兄なんかはいっぺんに七匹も釣り上げて。今日一番の大漁じゃなぁ!なんて言って、盛り上がりましたっけねぇ。
「大叔父は教師をしてたんですけれど、最後はボケてしまいましてねぇ。けっきょくそのまま病気で死んでしまいました。コロナのせいで帰るにも帰れませんでしたから、死に目にも会えんで。いまはもうお墓の中ですよ。
「うちの母方のお墓は山の上にありましてね。川を挟んで向こう側にある山でしたから、いっつも電車で通っとりました。母の実家がそっち側だったんですよ。毎年お盆とお正月の二回、母の実家へ挨拶に行くがてら、お墓参りをしたんですけどね。赤い色した橋があっちの山とこっちの山とを繋いでて、ちょうど橋の真下を川が流れとるんですけどね、その上を電車が走るんです。それがいっつも楽しみでねぇ。電車の中で兄といっしょにそらもうはしゃいではしゃいで。静かにしなさい!って親になんべん怒られたことか。ふふふ。天気がいいとね、橋を渡る時に電車の窓から海が見えたんですよ。川がずうぅっと流れていくその先に、山と山とに挟まれたその隙間にね、こううっすら、沈んでいく夕陽に照らされた波がゆらゆら、ゆらゆら揺れとるんがね、帰り道に見える時がありましてね。それを見とる時だけは、なぜだか不思議と静かな気持ちになって、おとなしくしてましたっけ。
「それにしても、こっちの夕焼けはずいぶん淡い色をしとりますねぇ。うちのふるさとは山に囲まれとるでしょう?そうすると、山が雲を呼び寄せますから、空に雲がない日なんてほとんどないんですけどね。その山が呼び寄せた雲がね、夕陽に焼かれて濃ゆい夕焼けになるんですよ。空が焦げたみたいにどす黒くなる日なんかもあってねぇ。夕焼けっていうのはそういうもんやと思うてましたから、こんなに淡い色した夕焼けもあるんやなぁって。これはこれで綺麗ですけどね。薄桃色に染まる時なんかは好きですねぇ。それでもやっぱり、時々ね、あの焦げつくような夕焼けが、無性に恋しくなる時もあるんですよ。」








